地震保険入る?入らない?2022.4.06
地震保険は入ったほうが良いの?とは、よく聞かれる質問ですが答えるのがとても難しい質問です。
まずは、地震保険の基本的な仕組みについてご説明します

・地震保険は単独では契約できません。火災保険にセットして契約する必要があります。
・地震保険の契約は、建物と家財のそれぞれで契約します。
・契約金額は、
火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内です。
・建物は5,000万円、家財は1,000万円が契約の限度額になります。
・保険料は、建物の構造と所在地により異なります。また、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
・「火災保険」の商品は損害保険会社によって様々ですが、「地震保険」はどこで入っても全く同じ内容です。
保険金の支払について
- 地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財が全損、大半損、小半損、または一部損となったときに保険金が支払われます(平成29年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合)
| 全 損 |
地震保険の保険金額の100%
(時価額が限度) |
| 大半損 |
地震保険の保険金額の60%
(時価額の60%が限度) |
| 小半損 |
地震保険の保険金額の30%
(時価額の30%が限度) |
| 一部損 |
地震保険の保険金額の5%
(時価額の5%が限度) |
<建物>
| 平成29年以降保険始期 |
基準 |
| 全損 |
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 |
| 大半損 |
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 |
| 小半損 |
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 |
| 一部損 |
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 |
<家財>
| 平成29年以降保険始期 |
基準 |
| 全損 |
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
| 大半損 |
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
| 小半損 |
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |
| 一部損 |
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
政府による再保険制度
- 地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。民間のみでは対応できない巨大地震発生の際に、1回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、現在、11兆7,751億円であり、民間保険責任額と合計した1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円です。(2021年4月現在)
- 総支払限度額は、関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲とされています。万が一、支払われるべき保険金の総額が総支払限度額を超える場合、契約ごとに支払われる保険金は削減されることがあります。
さて、保険というのは万が一の時にやはり入っていてよかったと思えるものですが、その万が一の時にどのくらいの保険が支払われるのでしょうか、簡単な試算をしてみましょう。
新築1戸建住宅を5000万円で購入(住宅ローン4500万円利用)
建物火災保険 2000万円(建物地震保険 1000万円)
家財火災保険 800万円(家財地震保険 400万円)
不幸にも購入後5年目に地震により被災してしまった場合、それぞれの被災状況(建物も家財も同様の被害とする)の保険金は以下のようになります。
全 損 建物 1000万円 家財 400万円 合計 1400万円
大半損 建物 600万円 家財 240万円 合計 840万円
小半損 建物 300万円 家財 120万円 合計 420万円
一部損 建物 50万円 家財 20万円 合計 70万円
なんだ結構もらえるんだと、思った方もいらっしゃるかもしれませんが、これでは、ローンも残るし再築は出来ないじゃないかというご意見の方もいらっしゃると思います。上記の大半損の判定の場合、家のほぼ半分の柱・壁・屋根が損傷(焼失)となっている家はなかなか修理して住むのは難しそうだなというのが個人的な感想です。
日本損害保険協会のデータによると、2012年3月1日時点で東日本大震災関連被害に支払われた地震保険は全国で約762,000件。総額は1兆2,167億円を超えました。そして将来、南海トラフ巨大地震が発生した場合には、その直接的被害額は東日本大震災の5〜10倍になると予想されています。10倍だった場合は、保険金の総支払限度額は12兆円という数字はぎりぎり足りるのか?と安心できるのかは、やや不安なところではあります。
そして地震保険は、「地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として」いる制度であって、建物や家財の再建築のための保険ではなく、費用の保険と考えるべき、被災した方が少しでも早く生活を安定させるための当座の資金を賄う事こそが地震保険の本来の役割なのです。
建物家財ともに、火災保険は再取得価格を基準とすることが出来ますが、地震保険金の支払いは「時価額」を基準としますので、木造の場合で築後40年や50年経過している建物では、保険金は殆ど支払われないこととなります(掛けられる地震保険料もわずかですが)
地震保険に入っているから「100%安心」ではなく、住宅ローンの残債の有無や、他の資産の状況などを考慮して、万一の時にご自身やご家族を守ることが出来るために何が必要かをじっくりと考えて契約することが必要なのではないかと考えます。
※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。


 シャーメゾンはこちら
シャーメゾンはこちら
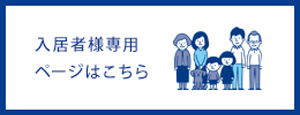
 ご入居者様専用ページはこちら
ご入居者様専用ページはこちら